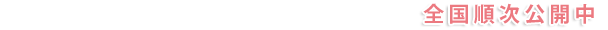介護をテーマにした映画というと、わざとらしいナレーションに情緒たっぷりの音楽で、「福祉の心」を謳いあげるものばかりだった。しかし、この映画の作り手たちは、それを伝える映像というものを信じている。だから、音楽やナレーションで演出しなくても、心は動く。拍手したくなったり、思わず吹き出したり、泣きそうにもなる。
これは、私たちがとっくに脱却したと思っている野蛮という人類史から、本当に脱却するための実践をしている人たちの記録である。
三好春樹(生活とリハビリ研究所 代表/「月刊ブリコラージュ」編集人)
予想を遥かに超えていた。
観ながらずっとこらえていた。でも最後の最後、思わず嗚咽がもれた。
徹底して抑制したスタイルが、そして加算ではなく減算した手法が、ドキュメンタリーの神髄を具象化した。
人間ってすごい。侮れない。愛おしい。そして切ない。それらを実感できる映画だ。
森達也(映画監督・作家)
介護保険をはじめ制度ができると、多くの人が救われ世の中の風景が変わる。
しかし制度そのものの持つ欠陥は、必ずその枠組からこぼれる人が出てくること。
私自身、もし自分が介護施設でお断りをくったらどうしょうと不安を感じる年頃になった。
はみ出し高齢者に居場所をつくるのは、制度ではなく結局人である。
とくに普通の若い人が乗り出していることに心安らいでいる。
樋口恵子(評論家)
介護する人も、介護される人も、
みんなみんな闘っている。
(これが現実だ)
これが今の日本だ、これからの日本だ!!
さあどうするどうする、どうすりゃいいんだ!!
毒蝮三太夫(タレント)
老いや弱さの持つ力をあらためて確認し「降りる生き方」に咲いた色とりどりの幸福の形に心が抱きしめられる。
寺田和代(社会福祉士、ライター/クロワッサン誌778号「女の新聞」より )
その人の〈ある〉が保障される場が居場所だ。
〈ある〉を保証するのに、余分なことはいらない。
そこに居続ける特定の、特別な誰かがいればいい。
その誰かに自分のまるごとが受けとめられていると感じたとき、
人は安定的に自分が自分であっていいのだと思えるようになる。
介護の基本は、こうした自足感を生み出すことではないか。
――家族の未来に一条の光が射して来る、そんな嬉しい気持ちで見終わったのだった。